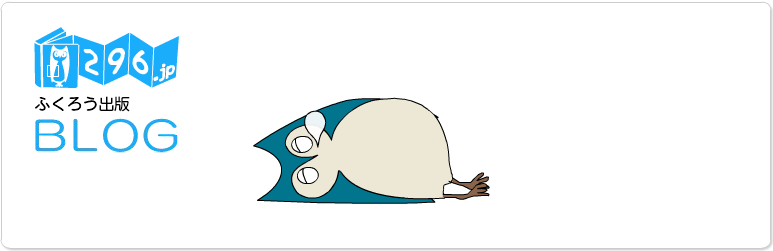先日、10月27日にアメリカ人のロック・アーティスト、ルー・リード (Lou Reed) が71歳で他界しました。
私は熱心なリスナーというほどではありませんが、1960年代末にヴェルヴェット・アンダーグラウンド (The Velvet Underground) のメンバーとしてデビューして以来、コンスタントに活躍してきた彼の「ロックのクラシック」作品は愛聴してきたし、独自の音楽性と媚びることやブレることとは一切無縁の存在には多くのロックファンと同様、リスペクトを感じていたので、まだまだ元気で活動してもらえるものと思っていた矢先の他界は残念です。
今さらですが、遺作となってしまった一昨年のアルバム “ LULU ” を購入、最後となってしまった肉声を聴きました。
エドガー・アラン・ポーの詩「大鴉」をテーマとするトータルアルバムで、俳優ウィレム・デフォーのポエトリー・リーディングであるタイトル曲を筆頭に静謐なイメージの曲が多い前作 “The Raven ” (2003) とはうって変わり、メタルロックバンドメタリカ (Metallica) との共演で当たり前ではあるものの、全編ヘヴィーな轟音の洪水である今作。
ドイツの19世紀の戯曲をベースにしたトータルアルバムという構成は文学博士という顔を持つルー・リードの真骨頂といえ、2枚組計87分、全10曲中3曲は10分を超える長尺の、最近めっきり少なくなった気合を入れ緊張感をともなって聴くことの求められる作品です。
確かにルー・リードの作品として聞くと、このヘヴィーさ、タイトさは異質のものです。でもスロー~ミディアムテンポの轟音に乗せてポエトリー・リーディングのような、ドスの効いたルー・リードのボーカルが出てくるとそこはもういつものルー・リードの世界。語尾を少し捻ったところが辛うじて歌メロ、というのも全くいつもの通り。相変わらずクールでかっこいい。
ただ、テンポアップしメタル独特のギター・リフが鳴り始めると、もうそこは紛れもないメタリカの世界。リズムのタイトさが際立ち(ドラムのインパクト大)、緩急の変化もスリリングで、アルバムいちばんの聴きどころがメタリカの熱気あふれるプレイであることは疑う余地のないところです。
↓ 2つの強烈な個性が火花を散らす “ ザ・ビュー ”
(アルバム ” LULU ” より)
レコーディングセッションの間じゅう、既存の方法論を棄て、ありきたりの考えから離れることを要求し続けたルー・リードとそれに応えてこの上ないパワフルなサウンド創り上げたメタリカのメンバーたち。メタリカのメンバー、ラーズ・ウルリッヒによると時に衝突も起こる緊張感あふれるセッションだったようですが、大半の部分をスタジオでの即興で作り上げるという手法に
「既存の殻にこもるなど意味の無いことだ」というルー・リードのメッセージを感じます。
はじめの印象ではサウンドが変わってもルー・リードの世界は変わらない、というのが強かったものの、ラーズ・ウルリッヒの回想談やライナーに紹介されているインタビューを見ながら繰り返し聞くうちに、
『エネルギー』、『重さ』、『大きさ』 (ラーズ・ウルリッヒ談)
つまりはメタリカの持つ圧倒的なサウンドのパワーやタイトネスがルーのインスピレーションに大きく作用しただろうな、と思えてきました。
この作品にはコラボレーションによるケミストリーが間違いなく生まれていると思うし、それゆえルー・リードとメタリカ双方が納得できる仕上がりで、それぞれの音楽に親しんできたリスナーに広く深く、この先長く受け入れられる傑作になっていると思いました。
メタリカのラーズ・ウルリッヒによるアルバムセッションの回想談
(2013年10月31日、ロッキングオンWebサイト洋楽ニュースより)
既存の殻にこもるなど意味の無いこと-
レコーディング当時69歳だったルー・リード。間違いなくその視点は未来を見据え、新たな方向性を模索していたと思われます。
ロック界のクラシックとされ、30~40年に渡ってシーンで活躍を続けながら、今も現役で精力的に制作活動を行っているベテラン・ミュージシャンに共通して言えるのは、自分で築き上げてきたものの上に安住することなく、新たな方法論を常に自ら模索している姿勢だと思います。
こうした姿勢は年齢とは無関係にロック的といえるし、生き様としてかっこいいですね。
生きている間に言ってくれよ、と叱られそうですね。
[” LULU ” ユニバーサル インターナショナル, 定価2,980円]
↓ おしまいにルー・リードのクラシックナンバー “ ワイルドサイドを歩け ”
(1985年のライヴから)