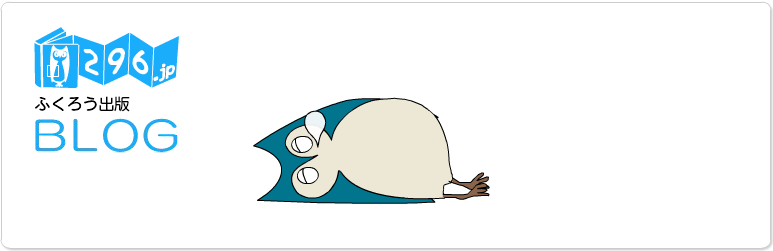モノクロの自然光を生かした映像、低くて重いゆっくりと発せられるオープニングのナレーション、そして静寂。このような静けさの醸し出す緊張感は日本特有のものです。
1962年に公開された時代劇の名作 『切腹』(松竹) は、こうして観る者すべてにサスペンスを予感させながら幕が上がります。ぞくぞくする、スリリングこの上ないオープニングです。
戦が無くなり、仕官の道が断たれた(仕事が無くなった)下級武士の悲哀をリアルに感じさせ、その日の暮らしすらおぼつかない中でも武士たちが尊重する 「武士道」 とは何なのかを問いかける脚本が素晴らしく、仲代達也、三國連太郎、丹波哲郎らの重厚な演技と、悲哀・苦痛・残酷・冷笑などさまざまな人間の感情を陰影濃く捉えたモノクロ映像にひと時も目をそらすことはできません。
ラスト近く、尾羽打ち枯らした津雲半四郎が武家に伝わる祖先の甲冑に倒れ掛かるシーンがこの映画のテーマを象徴しています。
1962年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞。国内よりも海外(欧米)で注目され、高く評価される作品というのがときどきありますが、この作品も典型的なそれだと思います。
まだまだ観たい昭和の名優、名演技
三國連太郎さんが亡くなった後、5月にこの映画と『復讐するは我にあり』(今村昌平監督)、そして『戒厳令』(吉田喜重監督)を借りてきて再鑑賞しましたが、この『切腹』も含めて「娯楽」と呼べる要素はほとんどなく、社会派ドラマだったり観念的な作品だったりで、観ていて何かを考えさせられるものばかりでした。
返して言えば、単にその時面白ければいい、というのでなく、観る者の記憶にいつまでも残る、深い感銘を刻み込むことを目指したような作品に、三國さんという役者さんは特に欠かせない存在だったのではないでしょうか。
政治的理由でもあるのかDVD化されていないのですが、『閉鎖病棟』で知られる帚木蓬生原作の日本アカデミー主演男優賞を受賞した主演作『三たびの海峡』をいつかぜひ観たいです。
きっと原作同様、一度観たら忘れられない映画だと思います。
「切腹」(1962、日本。監督:小林正樹 主演:仲代達也、三國連太郎)