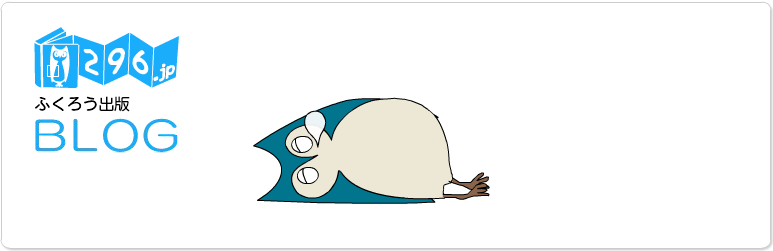[映画 『日輪の遺産』 鑑賞記]
原作は文庫で500頁を超える大作。尺に収めるためには、どこかを端折らなくてはいけないんじゃないか…。
そう思っていたところ、やはり登場人物にはかなり大胆な設定変更が。
しかし、物語は淡淡と進み、主人公である軍人と教師の“大人”役俳優は演出も控えめで、特に印象に残る台詞も無いまま進んでいく。
屈託なく笑い、歌う少女たちの姿ばかりが印象的。
そうか、これは少女たちの映画なんだ、と途中から気づかされる。
13~14歳の、女学校の生徒20人(キャラクターを際立たせるためか、人数が原作よりも大幅に少なくなっている)。
朗らかに響く少女らの歌声。
「出てこい、ミニッツ、マッカーサー、出てくりゃ地獄へ逆落とし」
醜悪な歌詞と屈託のない少女らの笑顔、朗々とした歌声、そのアンバランス。
エンディングも近づき、8月15日が来て戦争は終わった。
しかし、13~14歳という、まだあどけない少女たちにはやることが残されていた。
彼女たちには自らの身に引き換えてでも守るべき、さらに小さな存在、小さな平和、小さな未来があった…。
8月15日が来たからといって、いきなり
「戦争は終わった、明日から復興だ、新しい日本を築こう」
と前向きになれたわけはない。
一家の柱である父親は戦地に取られて死んだり消息不明…。
片や、生還したことを恥じて人目をはばかる人もいる。
誰もが明日の暮らしの何1つの保障もない。
幼い弟や妹を飢えさせずに生かしたい。
乳離れすらしていない赤ん坊を死なせたくない。
でも、どうすれば…。
明日のため、家族というちっぽけでも2つとない自分自身の世界を守るため、必死に戦後を生きた先人たちについて、往時を生きていない私たちは到底知る由もなく語る資格はないのですが、せめて自分自身に問いかけてみよう、とそんなことを考えさせられる映画でした。
『日輪の遺産』(浅田次郎、講談社文庫、1997)
[辺見じゅん著 『戦場から届いた遺書』 読後記]
先月、9月21日に亡くなった女流作家 辺見じゅん氏は戦地に赴いた兵士の日常生活、家族への思い、望郷の念などをその日記や戦地からの手紙、あるいは遺書などに綴られた「小さなことば」に見出し、粘り強く綿密に取材を重ねては、当時の人びとの真の心に迫り、後世に伝えることに腐心し続けた方です。
この本は、太平洋戦争中、戦場に赴いて二度とふたたび家族に会うことなく死んだ兵士たちの綴った遺書の「小さなことば」に込められた切実な思いを伝えるセミ・ドキュメント。
終戦間際に突如侵攻したソ連軍に捕虜として取られ、戦争はとうに終わったのに収容所で無念の死を遂げなくてはならなかった45歳の父親が子どもに語りかけた「遺言」を読んで、思わず身震いし身のすくむ思いがしました。
『戦場から届いた遺書』の結びで
「死者たちの小さな、しかし真実の叫びに耳を傾け、歴史の真実を知ること」
の重要性を著者 辺見じゅん氏は説き、死者たちの声こそが21世紀の日本を生きる現代の日本人への遺産であると述べ、彼らが私たちに遺した「遺言」と、今の日本は全く裏腹の姿になっているのではないかと警鐘を鳴らしています。
日本人である私たちの心の中に、死者は間違いなく生き続けている。
彼らの死が無駄になってはいけない。無駄にしてはいけないと、考えずにいられません。
それにしても、こうした労作があってこそ、平和を享受して生きる私たちが、たとえおぼろげにであっても、大きな時代の潮流に翻弄され若くして死なないといけなかった人びとの心の声を感じ取ることができるのですよね。
辺見氏の遺志に感謝し、ご冥福をお祈りします。
まったく今年という年は、震災とか原発事故とか9.11から10年とかいろいろなことが重なって、いろいろなことを考えさせられずにいられない年ですね。
『戦場から届いた遺書』(辺見じゅん、文春文庫、2003)
『男たちの大和』(上)(辺見じゅん、ハルキ文庫、2004)
実弟 角川春樹氏により映画化されたこの作品、
映画の印象が強いですが、こちらも乗艦していた人びとの内なる声、
その思いに迫る、胸熱くなる本です。
『最後の言葉』(重松 清・渡辺 考、講談社、2004)
戦地で回収された兵士の日記をよりどころに、彼らが何を見、何を考えて生きたかを探ったルポルタージュ。
※ 単行本は品切れのようですが、文庫が出版されています。