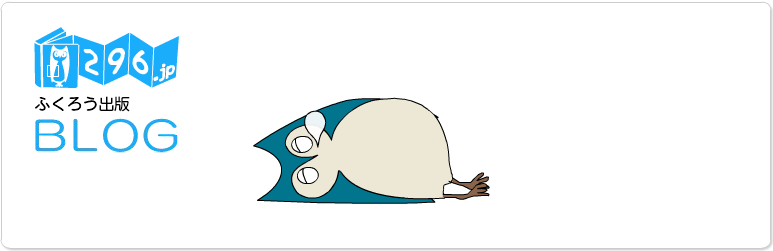「あとから、せんぐりせんぐり生まれてくるわ」
-『小早川家の秋』(小津安二郎 脚本・監督、
原 節子、中村鴈治郎、森繁久弥他 出演、東宝、1961)-
「あとから、せんぐりせんぐり生まれてくるわ」
「せんぐりせんぐり」とは、「繰り返して、順繰りに」との意味。関西の言葉でしょうか?起源の古い言葉なのでしょう。
この短い台詞に、吉田喜重監督が評論の中で繰り返し述べている「小津映画の小津映画たるゆえん」が垣間見えた気がしました。
エンディングも近づいた一場面、珍しく端役での登場だった農夫役 笠智衆さんの台詞です。
晴れ渡る秋の虚空に突き出した火葬場の煙突から噴き出す煙。
川岸で農具を洗いながら、夫婦の農夫がそれを眺めている。
若い人だったら気の毒だと同情する妻にこたえて、夫は冒頭の台詞をひとり言のようにつぶやくのです。
短くてさりげないため、聞き逃してすらしまいかねないこの台詞こそ、他の作品には見当たらない小津監督自身の独白、自らの死生観をつぶやいたものに他ならないと私には思えました。
「元来、人は来る日も来る日も昨日と同じ生活、反復を続けるもの。変わらぬ日常こそがドラマであり、そのドラマを撮り続けることを小津監督は自らに課したのではないか」
と評論『小津安二郎の反映画』の中で著者 吉田喜重監督が推察していますが、これを受け、僭越にも私は次のように思いました。
――親から子へ、子から孫へと、人びとは次の世代にバトンを繋ぎ、「血」が守られ生活が受け継がれていく。絶えることのない反復。それを最小限の言葉で端的に語ったのが、冒頭の台詞に他ならないのではないか。
――何も起こらぬ日常こそがドラマ……。逆説的ではあるが、小津映画を語る上でこれ以上の真理は見当たらないのではないだろうか?だからこそ、俳優たちは過剰な演技を一切排し、ごく自然に振る舞うことを徹底して求められたのではないだろうか。
「小早川家の秋」は松竹ではなく、東宝映画作品として作られ、封切られた作品です。
印象的なカラー、おなじみのカメラアングルなど映像はいつもながらの魅力あふれるものですが、松竹作品とはどこか違っていて、出演陣も、原節子さんら小津組のレギュラー陣に加えて中村鴈治郎や東映の個性派俳優、森繁久弥、宝田明、小林桂樹、新珠三千代がずらっと顔を並べ他流試合のイメージもあります。
それでも、相変わらず女優さんらは皆とても美しいし、秋真っ盛りの大阪、京都の古い街並を美しく切り取った枕カット等、小津監督ならではの熟練の技、演出が冴えわたっています。
また、この作品に限ったことでなく、小津映画のもう1つの得がたい魅力として、脚本や演出で家族を思いやる人びとの美しい心持、そして美しい穏やかな日本語を丹念に描いていることが挙げられると思います。
「秋日和」で親子を演じたばかりの原節子さんと司葉子さんが義理の姉妹に姿を変え、京都・嵐山の桂川のほとりを会話を交わしながら歩くシーンがありますが、画面から美しい日本人の心がにじみ出てくるようで清清しい感動を覚えます。
小津監督の映画作品が欧米など海外で高く評価されていますが、1つには、こうしたつつましくて美しい日本人の姿が好感を呼び、作品の評価につながっているのではないかとも思われ(勝手な解釈ですが)、日本人であることを非常に嬉しく誇らしく思う気持ちになれます。
1960年の「秋日和」に続いて主演した原節子さんにとって、この映画は最後の小津監督作品の出演となりました。
小津監督の没後、一切の芸能活動を中止して引退した女優 原節子としても最晩期の作品といえると思います。
「小早川家の秋」(小津安二郎 脚本・監督、
原 節子、中村鴈治郎、森繁久弥他出演、東宝、1961)